
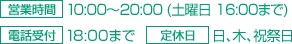

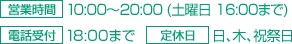
2025年7月6日
腰椎分離症は、特にスポーツをする若年層から、慢性的な腰痛に悩む中高年まで幅広くみられる疾患です。腰椎の椎弓部分が疲労によって骨折し、分離状態となることで発症します。この記事では、分離症の種類と症状、回復の目安、再発予防までを含めて詳しく解説します。
腰椎分離症は、椎骨の後方部分(椎弓)が分離してしまう状態です。この分離は、繰り返しの運動や過度な伸展・回旋動作などの疲労によって引き起こされることがほとんどです。
分離していても必ずしも痛みを伴うわけではありませんが、痛みがある場合には分離部に炎症や不安定性が関与している可能性が高くなります。
また、分離症は「片側分離」か「両側分離」かでも分類できます。片側のみの分離であっても、腰椎の回旋ストレスにより痛みが出ることがあります。両側分離になると椎体が前方にずれる“すべり症”へと移行するリスクもあります。
分離症やすべり症の典型的な症状には、以下のような特徴があります:
痛みは腰部に集中することが多いですが、すべり症に移行すると下肢のしびれや痛みが出ることもあります。
最短での回復は約3か月とされていますが、これはあくまで症状が落ち着くまでの期間であり、骨の分離そのものが治るわけではありません。実際には、骨癒合が得られないまま症状が改善するケースが多数あります。
しかしこの場合、再発のリスクが高いという問題があります。日常生活やスポーツなどで、再び過剰な負担がかかることで痛みが戻ってくる可能性があるのです。
分離症やすべり症は「結果」であって、真の原因は別の部位にあります。
分離症やすべり症において、腰仙関節(L5-S1)の弾力や安定性の欠如が共通してみられます。この関節に集中して負荷がかかることで、椎弓に過剰なストレスが蓄積し、分離を引き起こしてしまうのです。
股関節の屈曲・伸展・回旋の柔軟性が低いと、その動きを補うために腰が過剰に動くようになります。また、胸椎の可動性が失われていても、腰部が代償動作として無理な伸展や回旋を行うことになります。
腹筋や背筋などの支持性が低下すると、腰椎は不安定となり、小さな力でも損傷を受けやすくなります。
症状を改善し、再発を防ぐには、局所の対処だけでは不十分です。以下の要素が必須となります。
分離症やすべり症において、最も効果が高いのが腰仙関節の弾力回復です。関節ニュートラル整体では、腰仙関節の“あそび”を細かく評価し、微細な調整を行うことで、動作時の過剰な負担を取り除きます。
股関節・胸椎の弾力を回復させ、代償動作が起きない体を作ります。特に以下の可動域を確保することが必要です:
柔軟性だけでなく、体幹の支持性を高める運動療法が必要です。
分離症・すべり症は単なる骨の問題ではなく、全身の動作のエラーの結果として起こります。
症状の改善にも再発予防にも、腰仙関節の調整と、股関節・胸椎を含めた全身のの弾力回復、柔軟性や支持性の再構築が不可欠です。
関節ニュートラル整体では、全身の関節を200個×8方向(計1600通り)の動きで評価・調整することで、根本的な原因を探り、改善へ導きます。
腰痛がなかなか良くならない、何度も同じ痛みを繰り返すとお悩みの方は、ぜひ一度、関節ニュートラル整体を体験してみてください。