
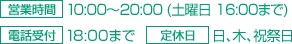

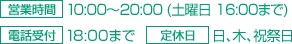
2025年8月3日
こんにちは。TOKYO腰痛肩こりケアセンターの仮屋です。
今日は、私が日々の施術で強く感じている「腰痛の負の連鎖」についてお話しします。
腰痛はある日突然やってくると思われがちですが、実際にはかなり前から“兆候”が始まっています。
そして、その兆候を見逃したまま放置すると、やがてぎっくり腰や椎間板ヘルニアといった大きなトラブルに発展してしまいます。
その典型的な流れが、
可動域制限 → ぎっくり腰(単発) → ぎっくり腰(複数回) → 椎間板ヘルニア(重度の腰痛)
というものです。
この順番で進行してしまう確率は、想像以上に高く、施術現場では日常的に目にします。
腰痛の大半は、腰そのものが急に壊れたわけではありません。
多くの場合は、腰の周囲――特に股関節・骨盤・胸椎などの動きが少しずつ失われていくところから始まります。
例えば、
こうした状態は可動域制限のサインです。
この段階では痛みを感じないことも多いため、多くの方が「特に問題ない」と見過ごしてしまいます。
しかし、関節や筋肉が固くなったまま生活を続けると、腰への負担が日々蓄積されていきます。
ある日、ちょっとした動き――
こうした何気ない瞬間に、腰に激痛が走る。
これが俗にいう「ぎっくり腰」です。
ぎっくり腰は、実は**関節や筋肉の弾力低下が限界に達したときの“防御反応”**のようなもの。
腰の組織が「これ以上動くと壊れる」と判断し、筋肉を一気に硬直させることで動きを止めるのです。
実際には筋肉の膜が損傷している場合がほとんど。
単発のぎっくり腰であれば、適切な休養や施術で1週間程度で回復することが多いですが、ここで何も改善せずに生活を戻すと次のステップへ進みます。
単発のぎっくり腰で「とりあえず治った」と思っても、原因である可動域制限は残ったままです。
つまり、腰への負担は解消されていないため、また同じ状況が繰り返されます。
特に、
こういったパターンの方は慢性的な腰部不安定症に近づいています。
関節の弾力が失われ、腰椎の動きが不自然になり、周囲の靱帯や筋肉が常に過剰な負担を受ける状態です。
この段階では、腰痛は「日常の一部」になってしまい、少しのきっかけでぎっくり腰を再発する体質になります。
ぎっくり腰を繰り返すうちに、腰の組織は確実に摩耗・損傷していきます。
特に椎間板と呼ばれる腰のクッション部分が、何度も強い圧力を受けることで徐々に変形。
最終的には椎間板が後方に飛び出し、神経を圧迫して椎間板ヘルニアとなります。
椎間板ヘルニアになると、
など、生活に大きな支障が出ます。
軽症であれば保存療法で改善しますが、重度の場合は手術が必要になるケースもあります。
この流れの中で、唯一確実に介入できるのは「可動域制限」の段階です。
ぎっくり腰を何度も経験してからでは、回復に時間がかかるだけでなく、再発のリスクも高まります。
当院で行っている関節ニュートラル整体は、
「筋肉」だけでなく「関節の弾力」まで回復させることを目的としています。
腰痛の負の連鎖を断ち切るためには、
が不可欠です。
この手技は、まさにその条件を満たすために有効な方法です。
腰痛は、ある日突然起こるわけではありません。
その多くは、
可動域制限 → ぎっくり腰(単発) → ぎっくり腰(複数回) → 椎間板ヘルニア(重度の腰痛)
というステップをたどります。
そして、この連鎖を止める唯一のタイミングは、可動域制限の初期段階です。
「まだ痛くないから大丈夫」ではなく、「まだ痛くないうちに整える」ことが何より大切です。
腰の不安がある方、動きの固さを感じる方は、ぜひ早めにご相談ください。
負の連鎖を断ち切るお手伝いをいたします。