
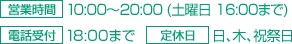

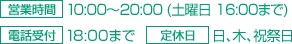
2025年8月5日
~可動域制限の原因を正しく見極めるために~
こんにちは。
TOKYO腰痛肩こりケアセンターの仮屋です。
腰痛や肩こり、膝の痛みなど、日常生活の質を下げてしまう関節痛。
その多くは「可動域の制限」から始まっています。
可動域が狭くなると、動作のパターンが崩れ、姿勢が乱れ、最終的にはどこかの関節や筋肉に過剰な負担がかかる──これが痛みの大きな流れです。
では、その可動域はなぜ減少するのでしょうか?
そして「どこが」制限されているのでしょうか?
今回はこの問いに対して、「組織」と「場所」の2つを区別して考えることの重要性をお伝えします。
可動域制限を分析するうえで大切なのは、
この区別ができないと、せっかく施術やセルフケアをしても的外れになり、改善までの時間がかかります。
まずは「何が」固くなっているのかを知ることが大切です。
最も思いつきやすく、かつ可動域制限を起こしやすいのが筋肉です。
筋肉は骨と骨をつなぎ、関節を動かす主役です。
しかし、疲労や長時間の同一姿勢、ケガなどで筋肉が縮こまると、動きが大幅に制限されます。
筋肉は最大の制動要素であり、しかも可動域を制限する代表格です。
筋膜は筋肉を覆う薄い膜で、全身を立体的に包み込んでいます。
筋膜がねじれたり癒着したりすると、筋肉が伸びる前に膜が制限をかけます。
感覚としては「伸びている」というより「引っ張られて動かない」感じ。
筋膜の癒着は一方向だけ制限することも多く、見落とされやすいポイントです。
関節を包む関節包や靱帯は、関節の安定性を守る組織です。
ケガや長期の不動、加齢などによって硬くなり、関節の最終可動域で「詰まる」感覚が出ます。ただし、緩すぎてこれ以上動いてはいけない場合でも「詰まる」感覚に陥ることもあるため注意が必要です。
関節の制限は筋肉や筋膜と違い、ストレッチではなかなか改善しません。
筋肉が固いのに関節を操作しても効果は薄く、逆に関節が固いのに筋膜だけをほぐしても改善はしにくい。
それぞれ別のアプローチが必要です。
例外的に、筋肉は骨についているため、関節を動かすことで筋肉もついでに緩むことがありますが、これは“副産物”と考えるべきで、根本的な改善には的確なアプローチが欠かせません。
次に大切なのは「どこが」固くなっているのかを突き止めることです。
これは痛みのある場所と一致するとは限りません。
このように、痛みが出ている場所と、可動域制限がある場所が別であることは珍しくありません。
むしろ臨床の現場では、このパターンの方が多いと感じます。
人間の動きは連動しています。
股関節が固ければ腰椎が代償動作として過剰に動き、結果として腰痛を起こします。
手首が固ければ肘や肩が代わりに動き、肘の炎症や肩こりの原因になります。
歩く、走る、物を持つ、ひねる──すべての動きは全身を使った連動運動です。
どこか一か所の可動域が狭くなると、別の場所に負担が集中します。
この「代償動作」が長く続くと、その部位もやがて痛みを出すようになります。
可動域を改善するためには、
当院の「関節ニュートラル整体」では、全身の関節を丁寧に検査し、動きの硬さや弾力を確認します。
そして、固さの原因が筋肉なのか、筋膜なのか、関節そのものなのかを判別し、それぞれに適したアプローチを行います。
約200ある全身の関節を8方向に検査し、どこが固く、どこが緩みすぎているのかを確認します。
筋肉の問題か、筋膜の問題か、関節の問題かを切り分けます。
痛みのある部位だけでなく、連動を阻害している隣接関節や遠隔部位も含めて評価します。
筋肉は筋肉、関節は関節、筋膜は筋膜というように、それぞれに適した手法で改善を促します。
改善した可動域を日常動作で活かすために、正しい動かし方や姿勢を指導します。
関節痛の本当の原因を見つけるためには、「痛い場所」だけを見るのでは不十分です。
動きの制限がどこにあり、何によって起きているのかを見極める──これこそが、根本改善への最短ルートです。
もしあなたが長年の腰痛や肩こり、関節痛に悩んでいて、色々試してもなかなか良くならないとしたら、それは**「組織」と「場所」を正しく区別できていない」**可能性があります。
気になる方はぜひ一度、当院で全身の動きをチェックしてみてください。