
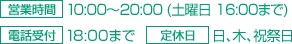

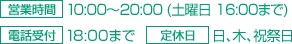
2025年9月16日
こんにちは、TOKYO腰痛肩こりケアセンターの仮屋です。
「ストレッチをすると筋肉が伸びて柔らかくなる」――多くの方がそう思っていませんか?でも実は、筋肉そのものはゴムのように伸びるわけではありません。筋肉は本来「縮むための組織」であり、柔軟性が高まるのは別の理由によるのです。
そして、この理解を深めるために欠かせないのが、筋肉の中で働く「アクチン」と「ミオシン」の役割です。さらに、体をしなやかに保つために有効な方法として「コントラクトリラックス」「ホールドリラックス」を応用した 腰痛肩こりケア体操 があります。今回はこれらをまとめてお伝えします。
まず最初に知っていただきたいのは、筋肉は「縮むこと」を得意とする組織だということです。
腕を曲げたり、物を持ち上げたりできるのは、筋肉が収縮するからです。逆に、筋肉が自分からグイグイと伸びていく機能はありません。
無理に伸ばしすぎれば肉離れのような損傷を起こします。ですから「筋肉を伸ばして柔らかくする」という表現は、厳密には正しくないのです。
では、ストレッチをしたときに「体が柔らかくなった」と感じるのはなぜでしょうか?
このように、柔軟性が高まるのは 筋肉そのものが伸びているのではなく、周囲の組織や神経の働きが変わっている のです。
ここで、筋肉がどうやって縮むのかを見てみましょう。カギとなるのが「アクチン」と「ミオシン」という2つのたんぱく質です。
この2つがかみ合って動くことで、筋肉全体が縮みます。
専門的には「スライディングフィラメント理論」と呼ばれる仕組みです。
この微細な働きが積み重なることで、私たちは力を出し、体を動かすことができます。
つまり筋肉は「縮む」ことが本来の役割であり、「伸びる」というのは外からの力でアクチンとミオシンが離れる受け身の状態にすぎません。
柔軟性を高めたいなら、筋肉そのものを無理に伸ばそうとするのではなく、「神経と膜の反応を変える」ことが大切です。
ここでおすすめしたいのが、関節ニュートラル整体の理論を取り入れた 腰痛肩こりケア体操 です。この体操の中心になるのが「コントラクトリラックス」と「ホールドリラックス」という方法です。
筋肉を一度グッと縮めてから脱力すると、その反動で筋肉がゆるみやすくなります。これを利用すると、普通のストレッチよりも安全に、しかも効率よく柔軟性を引き出すことができます。
筋肉を軽く収縮させ、そのまま数秒キープしてからゆるめます。これによって筋肉と神経が「緊張を手放してよい」と学習し、可動域が広がります。
上記の2つの方法は「筋肉を収縮させてから」という意味では同じです。ゆっくり伸ばすストレッチでは効果が出ない場合でもこれらの方法が有効なケースは多く効率的です。
腰痛や肩こりで悩んでいる方、柔軟性を高めたいけれど普通のストレッチでは効果を感じられない方には、この方法がとても有効です。体を無理に伸ばすのではなく、弾力を取り戻してしなやかに動ける体をつくる――それが、関節ニュートラル整体の考え方に基づいたケア体操なのです。