
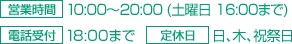

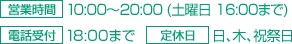
2025年9月12日
~首・肩こりから腰痛まで改善するために~
こんにちは。TOKYO腰痛肩こりケアセンターの仮屋です。
今回は「肩甲骨の動きとエクササイズ」について詳しくお話しします。
肩甲骨は上半身の動きにおいて中心的な役割を担っています。肩こりや首の痛みだけでなく、腰痛の原因にもなるほど全身に影響を与える部位です。すでに耳にしたことがある方も多いかもしれませんが、大切なことなので何度でも繰り返します。
結論からいえば、肩甲骨には 6種類の基本的な動き があり、その動きをまんべんなく行うことが健康な体づくりの土台になります。
肩甲骨は背中の左右にある三角形の骨で、鎖骨や上腕骨と連結しながら肩の自由な動きを支えています。
さらに大きな特徴として、肩甲骨は筋肉で体幹とつながっており、骨格として直接の関節結合が少ないため、動きの自由度が非常に高いという点が挙げられます。
そのため、動かさなければ固まりやすく、逆に適切に動かすことで全身の柔軟性や機能性を大きく改善できる部位なのです。
また肩甲骨は頭から腰まで広がる 僧帽筋 という筋肉でつながっています。首・肩・背中の緊張やこりに直結するのはもちろん、腰にも影響を及ぼすため「腰痛の原因が肩甲骨にある」というケースも少なくありません。
肩甲骨の動きは大きく6種類に分類できます。それぞれに必要なエクササイズがあり、バランスよく行うことが重要です。
肩甲骨を上に持ち上げる動きです。肩をすくめるような姿勢が挙上にあたります。
挙上の反対で、肩甲骨を下に引き下げる動きです。デスクワークで肩が上がりがちな方には特に必要。
肩甲骨を背骨に近づける動き。猫背改善に直結します。
肩甲骨を外に開く動き。手を前に伸ばすと自然に外転が起こります。
肩甲骨が外上方向に回る動き。腕を上にあげるときに不可欠です。
上方回旋の反対で、肩甲骨が内下方向に回る動き。物を下に引くときに働きます。
肩甲骨は 肩甲上腕関節(肩関節) と隣接しており、その可動性が不足すると肩の動きに制限がかかり、結果として肩関節に痛みや炎症が起きやすくなります。
また僧帽筋を通じて首や腰にまで影響するため、肩甲骨の動きが悪いと肩こり・首の痛みだけでなく腰痛のリスクまで高まります。
「肩がこるから肩をもむ」では根本改善にならないケースが多いのはこのためです。肩甲骨の動きを改善することこそが、肩こり・首痛・腰痛の共通の予防法になるのです。
肩甲骨は「上半身の要」といえる存在です。
この6種類の動きを意識したエクササイズを習慣にすることで、肩こりや首の痛みだけでなく腰痛までも予防・改善できます。
また、肩甲骨の自由な動きは肩関節の健康を守り、スポーツや日常生活のパフォーマンス向上にも直結します。
ぜひ日常の中に取り入れて、「動ける肩甲骨」「しなやかな背中」を手に入れてください。
👉 ご興味のある方は、TOKYO腰痛肩こりケアセンターで行っている「自分でできる腰痛肩こりケア体操」にもぜひご参加ください。肩甲骨を中心に全身の弾力を取り戻す方法を、実技を通じてお伝えしています。